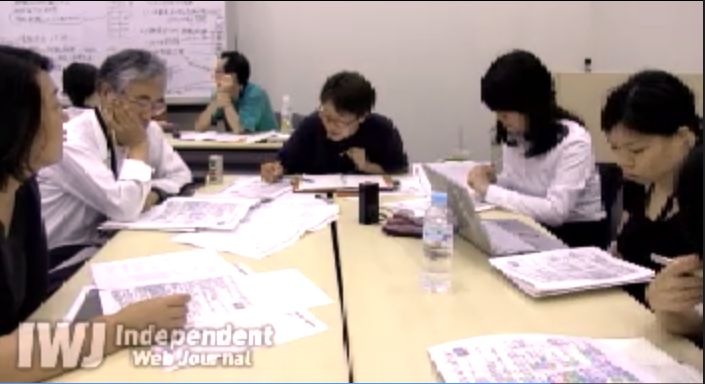
2012年9月21日(金)、東京都千代田区の参議院議員会館において、「原発事故子ども・被災者支援法市民会議 定例会議」が開催された。原発事故子ども・被災者支援法市民会議とは、2012年6月に成立した、原発事故子ども・被災者支援法の運用に被災者の声を反映させ、具体的な支援策の実現により、被曝の低減や健康被害の回避を目的に設立された。
この日は、出席者からの報告と質疑応答により、被災地支援が進んでおらず、被災者ニーズにも合っていない状況が鮮明になった。こうした背景の中、市民会議は他組織とネットワークを組みつつ、市民会議としてのアクションを進展させるため、5つの分科会による議論を深めた。
会議の冒頭、原発事故子ども・被災者支援法に関する、民主党のプロジェクトチームと復興庁および関係省庁との合同会議において、市民会議が出席し、その後、復興庁と打ち合せをした報告があった。各省庁からの情報によれば、現状では、支援法はなくてもよい仕分けになっているという。「現在の課題は、具体策以前に、支援対象地域の特定すら行われていないことであり、国会でその議論がなされている状況に留まっていることである」と報告者は述べた。
また、市民会議と日弁連およびJCN(東日本大震災支援全国ネットワーク)とのネットワークの枠組みが作られ、9月5日にフォーラムが開催されており、次回開催は、2012年10月13日であること、健康管理についても再検査やセカンドオピニオンに制限がかけられていること、支援法の第13条(放射線による健康への影響に関する調査、医療の提供等)に絡んだ、費用負担の軽減を含めた医療の充実について市民と行政にずれがあること、などが出席者より報告された。
さらに、この支援法を有効なものにするためには、被災者側からの積極的な提言が必要であることから、主に情報交換の場であった市民会議を、「線量等の測定と支援対象地域の設定」「健康診断・医療関連」「在住者支援」「避難者支援」の4つに、「広報」を加えた5つのグループに分けて、今後の活動を進めていくことが提案された。
分科会ごとの話し合いでは、「線量測定は、いつ、どこの測定を基準にするのか。具体的特定が難しい」「支援法の第13条を、どの省庁が担当するか曖昧である」などの声が上がり、それぞれの課題が浮き彫りになった。一方、広報活動としては、大手メディアへの働きかけ、ロゴマークの作成、著名人との連携などの方向性が提示された。【IWJテキストスタッフ・永野・澤邉・奥松】